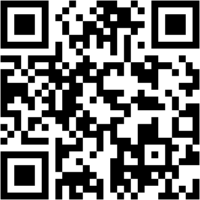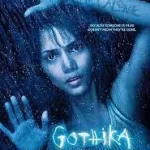最近では特別な日を感じることが難しいね。子供の頃は、クリスマスシーズンには街中でキャロルが流れ、新年を迎えると鐘の音が響き渡っていた。あの頃は経済が成長していて、一生懸命やれば何でもできるって雰囲気があったんだ。人々はプレゼントを交換し、新年の挨拶を交わしてた。何でも体当たりで手に入れていたって感じかな?今思うとそれが可能だったのか不思議だけど、その頃は音楽を作る時もリールテープに録音して、好きな部分をハサミで切って貼ってたらしい。(本当なの?)
著作権に対する意識が高まるにつれて、街から音楽が消えたのは大きかった。街のレコード販売の露店も著作権やメディアの変化で消えてしまい、その影響は大手レコード店にも及んだ。そんな理由で、音楽はもはや空間を満たし、人々の間を繋ぐことができなくなった。イヤホンを通じて頭の近くに留まる音楽は、ニアフィールド用に編曲され、空間感よりもディテールに重点が置かれるようになった。それでも、ツールの進化でインディーズやアンダーグラウンドの才能が一人でプロデュースする時代が開かれた。でも、その代わりに街は静かになった。
経済危機に直面し、社会の雰囲気も共存やコミュニケーションよりも生存や自立に関心を持たざるを得なくなった。今の大学生たちは以前のような文化の自由を享受するよりも、スキルアップや英語の勉強に気を配らなければならない。モバイルプラットフォームは生産者と消費者を直接つなげ、中間ビジネスを壊滅させ、非対面の時代を加速させた。今ではスマホを数回タップするだけで新年の挨拶や誕生日プレゼントもすぐに届けられる。🎁📱
変化を評価したいわけではないけど、心配になるのは事実だ。昔から文化として定着するためには、大衆に一般的に受け入れられるという壁を越えなければならなかった。それは決して簡単なことではない。筆からペンへ、馬車から蒸気機関への移行にも何十年もの時間が必要だった。人々がそれを理解し、受け入れ、適応する必要があったからだ。老人から子供までみんなが当然のように受け入れるためには、アナログ的なプロセスと時間が必要だ。それは自然の摂理でもある。文化の変化は進化とそのメカニズムが同じだからだ。一朝一夕に無花果の花が実の内側に咲いたり、カエルの尻尾が消えたりすることはない。
しかし、いつからかテクノロジーとそれを活用するテックやSNS企業がこの変化を主導し始めた。一番適応できる世代を狙い、そのフレームワークを強制的に拡散させた。老人たちはそれが何かもわからずにWi-Fiをつかみ、メッセージを送るために画面上の仮想キーボードを叩き、注文したいメニューが見えないキオスクの前に立たされた。まだ実体もないメタバースという言葉にもう疲れてしまうのは言うまでもない。👴📱
昔から似たようなことをしてきたけれど、こうした変化が本当に人類に必要なのか考える時がある。もっと詳しく言えば、必要性の判断よりも、こうしたものが受け入れられる過程と時間が適切かどうかの悩みだ。検証がしっかりされ、全員の暗黙の同意が起こる前に、こんなに急いで進めるのは本当に正しいことなのだろうか?🤔
人間の寿命は – ちょっと伸びたけど – まだ百年未満だ。永遠に生きたいけれど、そうはいかない。他の地球上の生物と運命は変わらないのだ。ならば、生きている間は幸せであるべきじゃないかな?誕生の奇跡を享受し、消えていくのは人間の使命だ。そして、それはすべての動植物の使命でもある。でも、その使命がシステムやフレームワークに振り回されるのは人間だけだ。🙈
あなたは今、幸せに生きていますか?
テクノロジーが幸せな生活を妨げると言いたいわけではない。しかし、それが人と人との関係を軽くするのは問題だと思う。その観点から見ると、オフラインとの繋がりを大切にするモバイルプラットフォームとは違って、メタバースはどうしても人と人との関係をリセットしてしまう。どんなに良く見ようとしてもそうは思えない。小説や映画の中の近未来がすべてディストピアであるのには理由がある。
テクノロジーの中で人との絆や連帯が消えて、暖かい体温が自分の周りから消えてしまうというのは、思った以上に寂しいことだ。ハートを押してくれる十万のフォロワーよりも、隣で一緒に涙を流し、慰め、手を握ってくれる友達一人のほうが、もっと自分を幸せにしてくれるんじゃないかな?👫
一年の始まりをゆったりと過ごしたくて、新年の朝に新海誠の「遥かなる未来に」を何度も聴いた。なぜかはわからないけど、この曲を聴くと心が落ち着くんだ。何よりも歌詞がとっても美しい。聴いていると、救われる気がするんだ。2022年、人類には救いが必要かもしれないから。🎶